- 10月
- 2025年11月
7月5日には到着していたMacBook Pro 15″ Retina(以下MBPR)ですが、諸般の撮影事情により手元を離れていました。ようやく戻ってきたのでこの3連休を活かして現在のMacBook Pro 15″(Early 2011モデル)から移行をしようと準備中です。
移行に際しては、新旧モデル間でスペックが同じ場合には、Macにおいてはほとんどなにも気にしなくても良いというくらいのレベルでデータ移行は簡単です。Windowsの移行が昔はかなり大変でしたが、もしかしたら今は簡単になっているのかもしれませんが、Macはこれ以上ないほどにシンプルです。
ただ、以前に自慢エントリーをここやここに書いたように、MacBook Pro (Early 2011)は内蔵ドライブを外して512GB SSDを2枚入れているので1TBという仕様になっています。メモリー容量は同じですが、データ移行という意味ではメモリー容量は関係ありませんので、問題は内蔵ディスク(MBPRはディスクとは言わないのでストレージと書いた方が正しいのでしょうか)の容量です。
移行先であるMBPRはフラッシュ768GBにアップグレードしているのですが、それでも1TBには足りません。実のところ、この点がこのMBPRを買う最大の躊躇ポイントでした。それでも、このRetinaディスプレイに惹かれ、薄さや軽さにも惹かれたので買うことを決断しました。
ということでかなりスリム化しないと入らない(実際に旧MacBook Proで使用しているディスク容量は700GBくらいだったのですが、空きがない状態というのも困るので)ということになります。なので、まずは古くてまったく使っていないファイルなどを削除、またはクラウドスペースへ移動したりして減らしていっています。
以前にも書きましたが、個人的にはあまり現状のクラウドサービスは、回線の確保、スピード、容量と費用から考えて実際に使える仕様ではないと思っていますし、外付けストレージを持ち運ぶということはしたくないので、1年以上触っていないファイルを中心に整理していくことにしました。
容量を大きい順に見てみると、ストレージを圧迫している原因の1位はiPhotoにため込んでいる写真でした。たしかに、最近は1枚あたりの写真容量が増えていますし、写真は古くなったから消そうということにはなりませんので単に溜まっていく一方ということになります。
その次がiTunesの音楽やビデオデータです。こちらも写真と同様に積み上がっていくことしかないので、もうずっと使い続けているわけですからある程度の容量は仕方ありません。
本当のことを言えば、写真でも「押さえ」のカットがあったり、ずっと聞いていないような曲もあったりするのですがその選別には相当な時間がかかるのと、ここは時間が解決してくれるのではないかということで、この2つはリストラ対象には含めませんでした。
そうすると、その他のファイルで削減していく必要があるのですが、ここで気づいたのですがなんとKeynoteファイルが200GBくらい使っていたのです。ビジネスミーティングでも、AUGMなどのイベントでもKeynoteでプレゼンテーションを作ることはかなり増えてきています。その中でも特に最近はビデオを組み込むことが出てきましたので、そうするとどうしても1ファイルあたりの容量が大きくなってしまいます。また、ミーティングやイベントによって、大枠は同じでも少しずつ変えていますので別ファイルとなっているために雪だるま式に増えていってしまうのです。
これは単に古いのを消せば良いという話でもなく、繰り返しやっているイベントでは以前のを見ながら作ったり、同じようなコンポーネントは使い回したりすることもあるのです。とはいえ、これを削っていかないといけないということで、こちらも1年以上前のファイルはごっそりと別ストレージに移動してしまうことにしました。
そして、なかなか限界というところまで差し掛かってようやく400GBくらい空いたので、とりあえずは移行しても問題ないくらいのレベルになったのではないかと思い、これから移行を始めようというところです。
このブログを書いたスタッフ

プレジデント
ほっしぃ
音楽からMacの道に入り、そのままApple周辺機器を販売する会社を起業。その後、オリジナルブランド「Simplism」や「NuAns」ブランドを立ち上げ、デザインプロダクトやデジタルガジェットなど「自分が欲しい格好良いもの」を求め続ける。最近は「24時間365日のウェアラブルデバイス|weara(ウェアラ)」に力を注いでいる。
コメントを投稿





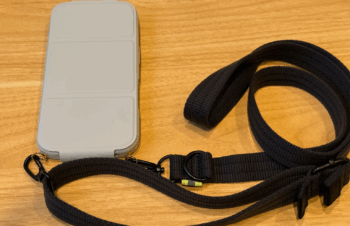

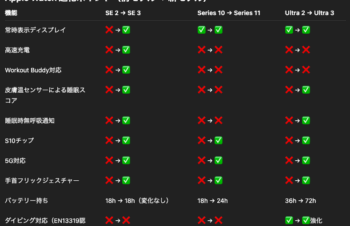

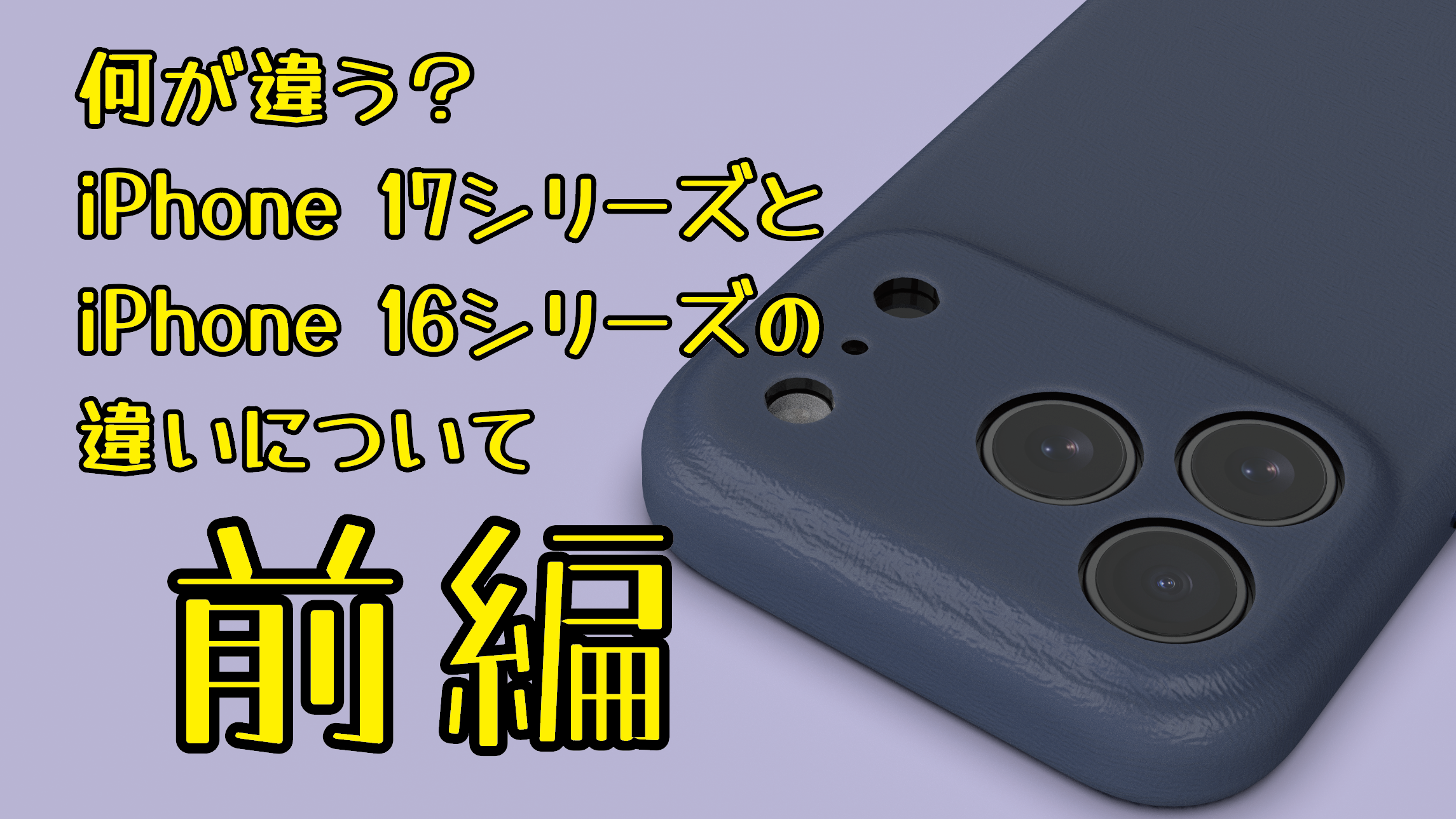



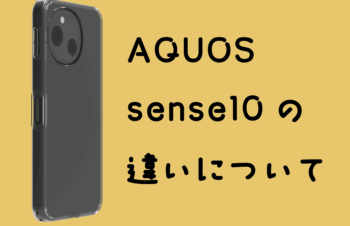








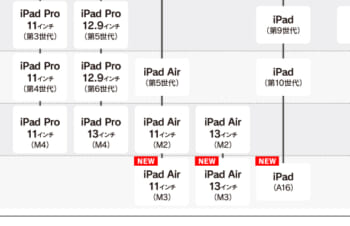



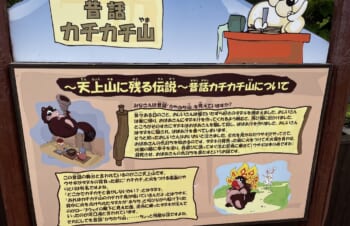

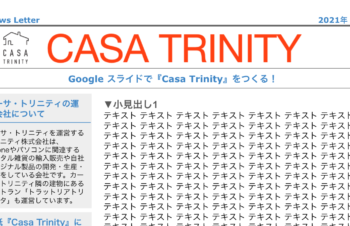

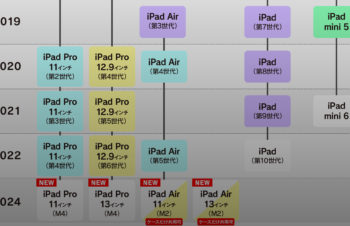
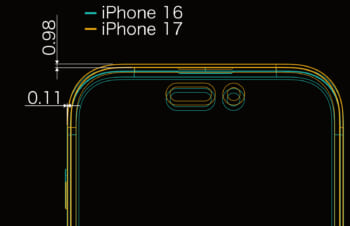






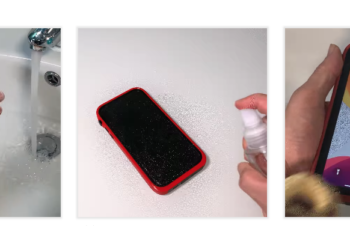








![NuAns NEO [Reloaded]向け、バッテリー交換キャンペーン実施](https://trinity.jp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0406-350x226.jpg)


名前とメールアドレスを入力してください。
管理者の承認後、コメントが表示されます。